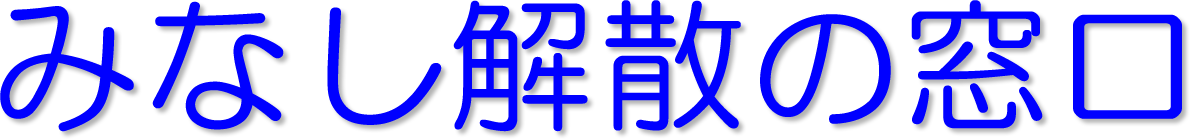みなし解散通知を放置して大失敗した事例
【事例①】取引銀行口座が凍結、資金が引き出せない
業種:建設業/会社規模:中小企業/登記放置歴:12年以上
▸ 状況
長年、代表者の変更や本店移転を登記せず放置。事業は継続していたが、2023年に「みなし解散」公告が出され、知らぬ間に会社が法的に「解散状態」に。
▸ 失敗内容
数ヶ月後、取引銀行が登記簿をチェックした際、「解散会社」であることが発覚。
→ 口座が「凍結」され、引き出しも振込も不可に。
→ 仕入れ業者への支払いができず、信用失墜。
▸ 結末
司法書士に依頼して復活登記を申請。すでに2ヶ月以上経過しており、急ぎで書類を準備し多額の報酬が発生。その間、売上に大きな打撃。

【事例②】補助金審査に落選、事業資金がゼロに
業種:飲食業/登記放置歴:15年/法人設立後の変更登記なし
▸ 状況
コロナ禍の影響で2023年、国の補助金に申請。審査段階で担当官が登記簿を確認。
→ 「解散会社」のため 不支給決定。
▸ 失敗内容
・実際には営業を継続していたのに、登記がされていなかったため「架空会社」と判断された。
・会社としての公的信用が完全に失われた。
▸ 結末
会社を復活させたが、再申請のタイミングを逃し、補助金も支援融資も得られず、翌月に閉店。

【事例③】M&A成立目前に白紙撤回、数百万円の損失
業種:IT/ベンチャー企業/登記放置歴:10年弱
▸ 状況
大手企業からの出資を受け、いよいよ株式譲渡の話が進行。
→ 登記簿謄本を提出した際に「みなし解散状態」であることが判明。
▸ 失敗内容
・相手企業から「法的リスクが高すぎる」と判断され、出資話が即座に白紙に。
・顧問弁護士からも「会社継続登記まで時間がかかる」と忠告を受ける。
▸ 結末
機会損失額:数百万円以上。将来の成長機会を自ら潰してしまう形に。

なぜ失敗は起きるのか?
|
原因 |
詳細 |
|
「登記は後でいい」と軽視 |
事業が順調だと手続きが後回しになりがち |
|
通知が届かない |
本店移転を未登記で通知書が旧住所へ |
|
法的知識不足 |
「12年登記しなければ解散」の制度自体を知らない |
|
コストを惜しんだ |
登記費用を節約しようとして放置 |
まとめ
みなし解散の通知を放置すると、表面上は問題がないように見えて、実はあらゆる信用や制度から排除されるリスクが生じます。登記は単なる事務ではなく、「会社の法的生命線」です。
ご希望があれば、このような事例を使ったWebページ用コンテンツ(図解やストーリーテキスト)にも対応可能です。